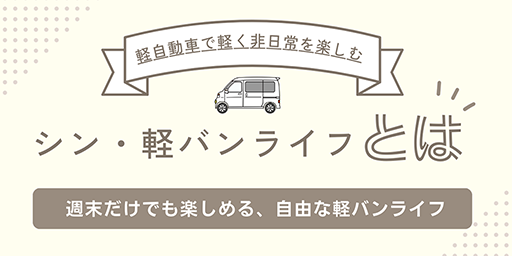【島根】出雲大社を深く知る:参拝とパワースポットの魅力
 ノマドマ
ノマドマ島根県のパワースポット「出雲大社」への旅。縁結びの神様として知られる古社で、歴史と神話の世界に触れるひととき。参拝のポイントから周辺情報まで、出雲大社の魅力を紹介します。
出雲大社鳥居


出雲大社には一の鳥居から四の鳥居まで4つの鳥居があり、それぞれ素材や形式が異なります。参拝時は鳥居をくぐりながら境内へ進み、神聖な空間へ導かれる象徴的な存在です。
写真にある出雲大社の二の鳥居(勢溜大鳥居)が2018年に建て替えられた主な理由は、1968年に建てられた従来の木製鳥居が約50年経過し、老朽化と耐久性の課題が生じたためです。
新たな鳥居には従来より4~8倍の耐候性を持つコルテン鋼(耐候性鋼)が採用されました。これは、長期保存性と安全性の向上、さらには防食性と景観の両立を図るためです。
出雲大社 参拝道


ムスビの御神像


ムスビの御神像は、出雲大社・銅鳥居の手前右側に1986年に奉納されたブロンズ像で、大国主大神(おおくにぬしのおおかみ)が「幸魂(さきみたま)」と「奇魂(くしみたま)」という2つの魂を天から授かる場面を表現しています。
このエピソードは『古事記』に基づき、大国主大神が神としての力やご縁を司る「ムスビの大神」へと昇華する大切な瞬間です。
「ムスビ」とは人や物事を結びつけ幸福をもたらす神聖な力を示しており、縁結びのご利益が全国に知られる由縁です。像の前には良縁や家族・友人との絆を願う多くの参拝者が祈りを捧げています。
また、その堂々とした姿は訪れる人々に神聖さや安らぎを感じさせます。
出雲大社 境内


出雲大社の境内は、八雲山を背に本殿や拝殿、複数の神社や文化財が立ち並び、松並木の参道や四つの鳥居が連なる神聖で荘厳な空間です。
自然と歴史が調和した、静寂と厳粛さ溢れる霊域です。
出雲大社の大しめ縄


出雲大社神楽殿の大しめ縄は、長さ13.6m、重さ5.2tという日本最大級の規模を誇る注連縄で、神域と現世を隔てる神聖な結界として奉納されています。
数年ごとに島根県飯南町で一年以上かけて制作され、伝統の技と多くの人の手により完成します。しめ縄の向きが通常の神社と逆であることも特徴です。
出雲大社 御本殿


出雲大社の御本殿は、1744年に建てられた国宝で、高さ約24m、正方形の「大社造」という日本最古の神社建築様式が特徴です。
9本の柱が田の字型に配置され、中央には太い心御柱が立ちます。本殿の神座は西向きで、社殿は南向きという珍しい構造。
内部天井の「八雲之図」や高床式の造りも見どころです。壮大な規模と厳かな雰囲気は日本最高峰の神社建築と称されています。
出雲大社 彰古館


彰古館(しょうこかん)は、出雲大社境内の北西にある1914年(大正3年)築の宝物館です。
木造2階建て・入母屋造銅板葺きで、国の登録有形文化財に指定。館内には大小の大国様や恵比寿様の像、神楽用の楽器類、神社伝来の古文書などを展示しています。
歴史的な建築美と出雲大社の信仰に関する貴重な資料が一堂に会し、訪れる人に出雲の歴史と文化を伝える施設です。
日本酒発祥の地 出雲のうさぎの杜氏


出雲大社境内には「日本酒発祥の地」にちなんで、杜氏姿のうさぎが日本酒づくりに励む石像があります。
うさぎは櫂(かい)を手に、酒タンクで一生懸命仕込み作業をしている様子が愛らしく、酒造の伝統と縁結びの地・出雲らしさを象徴しています。
神門通り




神門通りは、大正時代に国鉄大社駅と出雲大社を結ぶ参詣道として整備され、沿道には旅館や土産物店が立ち並ぶ門前町として栄えました。
車社会化や鉄道廃止で一時は賑わいを失いましたが、御本殿大遷宮などを契機に石畳舗装や街並み修景など再整備が進み、今では出雲大社の表参道として多くの参拝客や観光客が行き交う活気ある通りとなっています。


歴史的背景
- 創建は神代
出雲大社の創建年代は明確には伝わっていませんが、『古事記』や『日本書紀』など、日本神話に登場する神代にさかのぼるとされています。主祭神の大国主大神(おおくにぬしのおおかみ)が「国譲り」の後、天照大神からこの大社を賜ったという物語が有名です。 - 大社造という独自の様式
現在の本殿は1744年に建てられたもので、伝統の「大社造」様式(日本最古の神社建築様式)が継承されています。本殿の高さは約24mと非常に壮大で、全国でも唯一現存する大社造本殿(国宝)です。 - 国譲り・縁結びの神話
大国主大神は“縁結びの神”として広く信仰を集めており、出雲大社はその総本社です。国を造り、国を譲るという神話から、日本の始まりや国家統合の象徴ともなりました。
重要な祭典
- 神在祭(かみありさい)
出雲地方独特の神事で、全国の八百万(やおよろず)の神々が旧暦10月に出雲大社へ集まるとされます。神々の“会議”の間は「神在月(かみありづき)」と呼ばれ、縁結びや人々の運命に関する諸事が話し合われる神秘的な祭りです。 - 例大祭
毎年5月に行われる、出雲大社最大の年中行事。本殿で古式に則った厳粛な神事が執り行われます。 - 大遷宮
60年に一度の大規模改修・御神体の遷座が行われる伝統的な祭。社殿の保存・修理とともに、地域一体となった盛大な祭典となります。最新の大遷宮は平成25年(2013年)でした。 - その他、正月祭や節分祭、初詣、結婚式なども有名で、年間を通じて多くの神事や行事が行われています。
出雲大社はその歴史の古さと神話的意義、そして日本全国から人が集まり縁を結ぶ特別な場所として、今なお大きな信仰と文化的価値を持ち続けています。
出雲大社基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 名称 | 出雲大社(いづもおおやしろ/いずもたいしゃ) |
| 主祭神 | 大国主大神(おおくにぬしのおおかみ) |
| 住所 | 島根県出雲市大社町杵築東195 |
| 電話番号 | 0853-53-3100 |
| 参拝時間 | 6:00~19:00 |
| 定休日 | なし(年中無休) |
| 創建 | 神代(詳細不明・日本神話に由来) |
| 本殿様式 | 大社造(たいしゃづくり、日本最古の神社建築様式の一つ/現本殿は1744年築の国宝、高さ約24m) |
| 主要行事 | 神在祭(旧暦10月)、例大祭(5月)、大遷宮(60年ごと) |
| 見どころ | 四つの鳥居、本殿、神楽殿(大しめ縄)、十九社、ムスビの御神像、松並木の参道 |
| 交通アクセス | JR出雲市駅よりバス25分、一畑電車出雲大社前駅より徒歩約10分 |
| 駐車場 | あり |
| 備考 | 全国有数の縁結び神社・日本屈指の神社建築、参拝や観光の定番スポット |
関連リンク


おすすめ記事